
ダンスというと、どんなものを思い浮かべるでしょうか?
...社交ダンス? ...日本舞踊? ...それとも民族舞踊?
そもそも、ダンスってどういう経緯で生まれたのでしょうか?
実は、未だにそのルーツは定かではありません。
とはいえ、鳥に良く見られる「求愛ダンス」など、本能的な動きや求愛のためなどがその起源という説が有力なようです。
そして、現代に残っているダンスとしては、大きく分けて「芸術」としてのダンスと「宗教」としてのダンスがあります。
「宗教」としてのダンスは、それぞれに意味を持ち、さまざまな形態があります。
「芸術」としてのダンスは、演じる者と鑑賞する者に分かれ、演者(=ダンサー)の動きを鑑賞して楽しむという形態です。物によっては参加型のものもあります。
ここでは「芸術」としてのダンスについて考えてみましょう。
ダンスの一連の動きを「振り付け」あるいは「振り」と呼びます。
最近では英語で「コレオグラフ(Choreograph)」や
「コレオグラフィー(Choreography)」などという方も居ます。
これを考える人を「振り付け師」、
あるいは英語で「コレオグラファー(Choreographer)」と呼び、
これらの人たちによって「振り写し」や「振り入れ」と呼ばれる、ダンスの振り付けを覚えるための練習が行われます。
事務的に書くと、とてもわかりにくいですね。
簡単に書けば、「振りを考えた人が、踊る人に教えて、みんなで踊っているところを、見て楽しむ」ということなのです。
ここでのポイントは「踊る人(=ダンサー)も楽しんでいる」ということ。
楽しく踊って、身体を動かして、見る側も楽しい。
こんな楽しいことって、他にあるでしょうか?

では、ちょっと、やってみましょう。
1. 首を、右に傾けます。
2. 首を、元に戻します。
3. 首を、左に傾けます。
4. 首を、元に戻します。
...できましたか?
...これが、「振り付け」です。
そう! 一つ一つの動きは、とても簡単なんです!
それでは、この「振り付け」の最初に1つ加えてみましょう。
0. 両手を腰に当てます。
...どうですか?
ちょっと、ポーズがダンスらしくなりましたね。
更に脚に動きをつけたら、もはや、ダンスそのものです。
ほら、簡単ですよね!
つまり、身体の各部分の動きを指定されて、その通りに動かすだけ!
...でも、それが難しい...なんて思わないでください!
遅いテンポから始めれば、それでいいのです!
体が自然と動くようになってから、少しずつテンポを上げてみましょう。
きっと、あなたもステキなダンスを踊れるはずです。

さて。ダンスそのものが、そんなに難しくないということをおわかりいただけたと思います。
では、一言でダンスといってもどんなダンスがあるのでしょうか?
一般的に知られるダンスから挙げてみましょう。
★社交ダンス(ソシアルダンス / ボールルームダンス)
★競技ダンス
★バレエ
★モダンダンス
★ジャズダンス
★ヒップホップ
★ブレイクダンス(ブレイキング)
★タップダンス
★リバーダンス
★アイリッシュダンス(アイリッシュタップ)
*『アイリッシュタップ』というものは無いと言う方もいらっしゃいますが、ここではイメージしやすくするために、名前として挙げさせていただきます。
★コンテンポラリーダンス
★レゲエダンス
★ワルツ
★ルンバ
★チャチャチャ
★タンゴ
★サンバ
★ストリートダンス
★ディスコダンス
★フラメンコ
★フラダンス
...などなど。どこまでを1つの括りとするかの基準は非常に難しいところです。
そして、ダンスのジャンルそのものが、まるで生き物のように色々と組み合わさって、新しいものが生まれます。最近では「ヒップホップジャズ」や「ジャズヒップホップ」と呼ばれるジャンルも登場しています。
更には各所にあるテーマパークで見られるようなダンスを総称して「テーマパークダンス」と呼ぶ方々もいらっしゃいます。
日本の「能」「歌舞伎」「日本舞踊」や、中国の「京劇」など、舞踏劇の流れから来ているものもありますね。
皆さんが見てみたいダンスはどれですか?
そして、皆さんがチャレンジしてみたいダンスはどれですか?

ダンスが何にいいのか...。
それが最初にお話したところにあります。
踊る人も見る人も楽しむことができる!これが一番です。
そして、ダンスを続けることで、普段から身体を動かすことができるので、普通なら怪我をしそうな動きにも対応できるようになります。
身体を動かすから、食事もおいしく食べられる!
その上、食事を食べたら、元気に動くことができる!
...この循環が、身体と心を元気にして、ダンスでステキな毎日を送れるポイントなのです!
ダンスを楽しむ! こんな自然で簡単なことに、あなたも足を踏み入れてみませんか?
 ダンスというと、どんなものを思い浮かべるでしょうか?
ダンスというと、どんなものを思い浮かべるでしょうか?

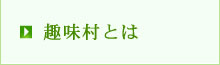
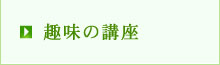



 では、ちょっと、やってみましょう。
では、ちょっと、やってみましょう。 さて。ダンスそのものが、そんなに難しくないということをおわかりいただけたと思います。
さて。ダンスそのものが、そんなに難しくないということをおわかりいただけたと思います。 ダンスが何にいいのか...。
ダンスが何にいいのか...。